小川国夫に関する2010年最大のニュースは映画『デルタ』の公開でした!
…と、言いたいところですが、それより『弱い神』(講談社)の刊行でしょう。

『弱い神』は、明治~昭和を生きたある家族とその周辺を描いた長篇ですが、
その最大の特徴は、この小説が、複数の人の《声》によって成り立っていることです。
小説には「人称」というものがあって、「私が」「ぼくが」といった一人称、
「彼が」「彼女が」「誰それが」といった三人称、そして「あなたが」「君が」といった
二人称など、いろいろな「人称」がありますが、『弱い神』はもっと複雑です。
いや、基本的には一人称で、いたってシンプルなのですが、語り手と聞き手が複雑に入り乱れて、
「複数の一人称」による多彩な《声》によって、物語が炙り出されているようです。
何という世界でしょうか。小川国夫さんは音楽を意識していたかもしれません。
たくさんの人によって奏でられる声のポリフォニーを聴いているようです。
『弱い神』に出てくる語り手たちは、小川国夫というひとりの作家のなかに
生まれた素晴らしいミュージシャンで、彼らは小川国夫という音楽にのって、
これでもか! というほど躍動しています。
『弱い神』のような作品とは、世界の文学史を見わたしても、
そうそう出会えるものではないでしょう。
下窪俊哉
「小川国夫」カテゴリーアーカイブ
島尾敏雄と小川国夫
大阪、シネ・ヌーヴォでの公開が、迫ってきています。
その初回である12/21(火)19時~上映の後には、
画家・作家で、小川国夫の著作の装幀・装画をたくさん手がけた
司修さんをスペシャル・ゲストにお迎えして、
小川国夫や絵画、映画、文学に関するイロイロサマザマな話を
ご来場いただく皆さんと共有したいと思っています。
その司さんが装幀を担当した小川国夫の著作を、またひとつ。

1987年刊行の『回想の島尾敏雄』(小沢書店)。
多くの方がご紹介されているとおり、島尾敏雄さんは、
朝日新聞の「一冊の本」で私家版『アポロンの島』をとり上げて
小川国夫さんが世の中に知られるきっかけになった作家です。
その交遊は、無名時代の小川さん(静岡県藤枝市在住)を、
島尾さん(鹿児島県の奄美大島在住)が突然、訪問して以来、
1986年に島尾さんが亡くなるまでつづきました。
この本は、その島尾さんの死後に刊行された、追悼文を含む一冊。
司修さんによる装幀(箱)も、控えめではありますが、
どことなく“追悼”を意識したような渋いものになっています。
下窪俊哉
小川国夫と大阪芸術大学(続)
2日間に渡る大阪芸術大学での上映にご出席くださった
学生の皆さん、ありがとうございました!
どんな感想をお持ちになったでしょうか?
本ブログやtwitterなどを通して、ご意見・ご感想はどしどし
お待ちしておりますので、よろしくお願いします!
さて、その大阪芸術大学で、小川国夫さんの責任編集として
出していた雑誌には『河南文学』(創刊号~第12号)のほかに
2003年に2冊だけ刊行された『河南文藝 文学篇』があります。
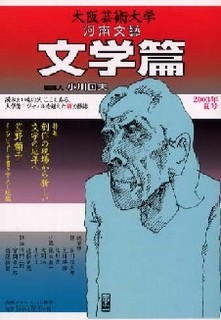
このように、小川国夫の肖像が表紙を飾った号もありました。
山藤章二さんのイラストです。
この号には小川国夫の大学での講義録が丸々一回分載っています。
「小説の方法」と題して、小川流の“ハウ・トゥー・ライト”を語ったものですが、
小説とは、「個人に深く関わること」だとしながら、
ホフマンスタールの言葉をひいて、自分の一生で耳に入ってくる“肉声”は
祖父祖母から孫の代、せいぜい曾孫の声までで、140年くらいか、と語っています。
まさに自分史です。ストレートな自分史ではないかもしれません。
もっと自由に拡大した自分史というものが、ぼくの小説です。
源氏物語は千年も昔の自分史ですよ。ぼくはその千年あとでも書くんです。
そう考えると、これは文学者のぼくの義務だ。紫式部がやったように
ぼくはぼくのフィールドでそれをやるんだという考え方が自然と出てくると
思うわけです。それが我々が文学をやる上の、
一つの基本に据えるべき考え方だと思います。
こういった話を重ねるなかで、生前最後の随筆集となった
『夕波帖』収録の「耳を澄ます」などの考え方が生まれたのだと感じます。
その話は、また。
※12/21(火)シネヌーヴォ初日上映&トークショーの予約の受付を
行っています。詳しくは、コチラをご覧ください。
下窪俊哉
小川国夫と大阪芸術大学
本日(12/13)から明日にかけて、大阪芸術大学の映画館にて
映画『デルタ 小川国夫原作オムニバス』の上映をさせていただいております。
映像学科の学科長で映画監督の大森一樹さんはじめ、
大阪芸術大学の関係者各位へは、心からお礼を申し上げます。
大阪芸術大学は、本映画の原作者・小川国夫さんが晩年の約16年、
文芸学科教授として深く関わった場所です。
学生の皆さんに、本映画がどのように届くのか、楽しみです。

その大阪芸術大学で、小川国夫さんを編集人として出していた雑誌があります。
『河南文学(かなんぶんがく)』という雑誌です。毎号の巻末には、
「編集後記に代えて」として、小川国夫さんの文章が掲載されていました。
創刊号の編集後記(に代えて)は、「文学的青春」というタイトルで、
後に『昼行燈ノート』(文藝春秋)に掲載されたものですが、単行本に掲載されている
文章とは、少しだけ雰囲気が違います。
ここで小川さんは、自分たち仲間で創刊した同人雑誌『青銅時代』の思い出について
書いています。私は大阪で小川さんと出会ったひとりなのですが、
この文章は、おそらく一生忘れないでしょう。
不幸から脱すること、癒えることを理想とした文学者は、自分に固有なこの軌道にひっそりと乗っている(あるいは乗ろうとしている)星のようなものだ。しかしこの星のかたわらには、軌道に乗ることをうけがわず、破滅を急ぐ星もある。その時その星は一きわ光を益すので、私は逃げて行く蛍を掌に収めようとするかのように、空しく手を伸ばしたものだ。そして闇を掴んで悲観にくれた悪夢に似た思い出は、もう二十二年も前のことなのに、まだ身近にある。
ここで「二十二年前」と書いてあることは、1991年の時点ですから、
いま、この時点で、約41年前の話です。
小川国夫さんの「文学的青春」は、大丈夫、まだ受け継がれているよ、
と呼びかけたい気がしています。
下窪俊哉
恋愛小説
小川国夫の小説には、若い男女の交わりを、すごく感覚的に
スケッチふうに書いた小品が幾つもあり、印象に残っています。
映画「誘惑として、」に登場する男女のエピソード
(短篇「駅の明り」を原作とする部分ですね)も、
そのエッセンスを伝えていると感じます。

短篇集『流域』のトップに収録されている「心臓」も、そういった作品のひとつ。
(画像は、集英社文庫版)
小川国夫のこの手の小説を、説明することは、どうしても難しくて、
良さを感じていただけるとしたら、本文をご紹介するのが一番良いのではないか、
と感じてひいてみます。
体についた綾子のにおいがした。蝉の声が夜気を引っ掻いた。一面の虫の声の底を、川が流れていた。彼は自分の動悸を聞きながら、この音だけが自分なのか……、と思った。騒ぐ血を肉の容器が柔らかく受け止め、ゴクンゴクンと波動を胸壁にぶつけていた。それも動物の感触だったが、一糸乱れないのが彼には不思議だった。どんな動物も体に心臓を持ち、混乱する意志と行為をよそに、揃って整然とこの音をさせている。そう感じながら、彼は長い間耳を澄ましていた。
とっても内省的な世界ながら、人間の「内面」に向かうというよりも、
音や、自然や、肉体といったモノに向かっているのが印象的です。
この本も久しく手に入らない状態がつづいています。
が、このアンソロジーは現行商品で入手可能でしょうか?
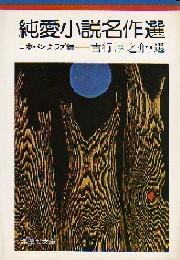
吉行淳之介選の『純愛小説名作選』(集英社文庫)。この本を開くと
島尾敏雄さんの「ロング・ロング・アゴウ」などと共に「心臓」も収録されています。
※12/21(火)映画『デルタ』シネヌーヴォ公開初日、19時~上映後に
小川国夫さんとも親交の深かった画家・作家の司修さんをゲストに、
本映画のプロデューサー仲田恭子とのトークショーを開催します!
シネヌーヴォでは予約受付を開始しています。お見逃しなく!
http://www.cinenouveau.com/news/news.html
下窪俊哉
遊子随想~旅の本
12/21のスペシャルゲスト・司修さんにちなんで、
司さんと小川国夫さんの“共演”作を今日も一冊。

1989年6月発行の『遊子随想』(岩波書店)は、
装幀だけでなく、本文中に置かれている絵も司修さんによるもの。

この本が刊行された当時、司さんの個展“遊子随想展”も開催されたとか。
司修『影について』(講談社文芸文庫)の巻末に置かれた
著者自身による“年譜”ではこの個展に触れて、
打ち上げで小川国夫さんと酒を「飲みすぎ」た出来事が
ユーモアたっぷりに書かれています。
『遊子随想』は、著者自身の、若き日のヨーロッパ放浪の旅を中心に
書かれた《旅》のエッセイ。傑作です。が、残念ながら現在は絶版。
ご興味もたれた方は、図書館か古本屋で探してみてください。
下窪俊哉
小川国夫&司修の仕事
司修さんが手がけた小川国夫関連の仕事として、何をご紹介しようか
と思って探しましたが、まずは、コレ。
2008年4月8日に小川国夫さんが亡くなったとき、
すでに予定されていて、没後に“遺作随想集”として刊行された
『虹よ消えるな』(講談社)です。
司さんは、この本のカバーと扉の装画、装幀を手がけています。

この本には、実は、映画『デルタ』プロデューサー仲田恭子の名前が登場します。
「骨折以降」という文章の後半に、出てきます。
小川さんは仲田演出の舞台を、藤枝市の蓮花寺池公園の畔にある野外劇で観たそうです。
するといきなり現われたシーンは、山の木だちのあい間に陣取った狐の群れでした。その狐こそ、退行に退行を重ねる私のかなたの極点にいる生き物と思えてきました。
と小川さんは(仲田演出の劇について)書いています。
そして、幼い日に聞いた狐の鳴声を鮮明に思い出して、
「退行の何なのかを教え、目を開かせ」られた、とつづけます。
今や私は忘却の霧のなかから、多くの宝を呼びもどしている、これは退行ではなくて、帰還だ、そのうちに私は、自分の生涯よりもはるかに広い時間の中に自分を解きはなつことができるだろう。
もともとは亡くなる9ヶ月ほど前に「日本経済新聞」に発表された原稿ですが、
こうやって書きながら、晩年の小川国夫のペンが伝えてくれる迫力をあらためて感じています。
下窪俊哉
幻想的で、現実的な小説
映画『デルタ 小川国夫原作オムニバス』、大阪シネ・ヌーヴォでの公開まで、
ちょうど残り2週間となりました!
先日のイベント“sdhellsong~耳よ、貝のように歌え”をご覧になった方にも
「小川国夫、知らなかったけど、読んでみてもいいな~」と思われている方が
少なからずいらっしゃると思います。(そう願います)
でも、いきなりどこから読めばいいのか、と言われてふと思い出したのが、
短篇小説のアンソロジー。つまり、複数の作家の小説を集めた本です。

これはそのひとつ。2001年6月から数年かけて刊行された講談社文芸文庫の
『戦後短篇小説再発見』というシリーズの第1巻です。
ここに、太宰治「眉山」、三島由紀夫「雨のなかの噴水」らと並んで
小川国夫「相良油田(さがらゆでん)」が収録されています。
(もともとは『アポロンの島』につづく第二作品集『生のさ中に』に収録されていた
珠玉の短篇ですが、現在、絶版状態がつづいています。)
憧れの(?)美人教師に「御前崎に油田がある」とデタラメを言った少年(浩)が、
ふたりで油田を探しに行く話ですが、途中から夢と現実が交錯したような世界に
どんどん踏み込んでいく。こんな言い方は危険かもしれませんが、
いかにも小川国夫らしい作品と言ってもいいかもしれません。
※12/21(火)シネ・ヌーヴォ公開初日(19時~)上映後に、
小川国夫さんとも親交が深かった画家・作家の司修さんをゲストに
スペシャルトークショーを開催します!どうぞご期待ください!
下窪俊哉
“傾聴”とは
関西上映先行イベント“shellsong~耳よ、貝のように歌え”ですが、
いよいよ今度の日曜に、迫ってまいりました!
井川拓の書いた昨日のブログを読んでいただければ、
“shellsong”が、そして映画『デルタ 小川国夫原作オムニバス』が、
ただ小川国夫の小説を“使った”だけの、悪戯な試みではないということを、
少しでも感じていただけると思います。
と、これにつなげて、何か“でかいこと”でも書いて大宣伝したいのですが、
どうもそういうのは苦手というか…。いや、ただ単に、ここでは違うことを書きたいのです。
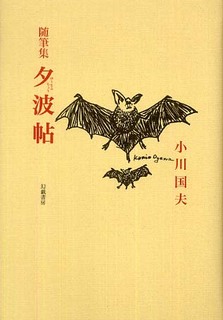
雑誌『新潮』2004年6月号に発表されたエッセイ「耳を澄ます」
(2006年12月に幻戯書房から発行された『夕波帖』に収録)には、
小川国夫流の“創作感覚”のようなものが書かれています。
タイトルから想像できると思いますが、ここで書かれているのは、
“聴覚”について、“音”について、です。
が、聴覚を含めた“五感”とは「便宜的な分けかた」であって、
「たがいに色層がにじみ合った虹のようなもの」とも書かれています。
ここで小川さんは(作品名こそ明記していませんが)
自身の短篇小説「ハシッシ・ギャング」の舞台裏の楽屋を披露しています。
(もちろん映画『デルタ』の原作のひとつとなった、あの小説です)
これは実験小説のたぐいです。勿論理想の小説ではありません。
理想からかけ離れた出来栄えです。しかし、けなげにも、はるかに遠い理想を、
私は追いかけているつもりなのです。なぜなら、私は、この一篇に
傾聴とは何かを集約したいと願って書いたのですから…。
テレビや政治家がしきりに助長している饒舌の時代に、
文句をつけたいわけではありません。
私の願いはただ一つ、傾聴の世界を書きたいのです。
この文章を読めば、小川さんが小説を書くことを通してずっと考えていたことは、
社会問題とか、まして風景描写とか音の表現といった
単純なことではまったくなかったことがよくわかると思います。
“傾聴”とは、何でしょうか?
いま、たとえば福祉、医療、教育など(あるいはビジネス?)の世界で、
よく言われる言葉と聞いています。
ただ、さりげなく「耳を澄ます」と書いた小川国夫さんに、思いを馳せています。
下窪俊哉
小川文学への招待、その一例
聞くところによると、チラシ配り担当(?)の暁雲さんは“マッチ売りの少女”状態だそうで、
貴重なチラシを燃やして暖をとると、小川国夫さんが「出たぞう」なんて
言って現われて、「イッパイやろうか」って赤提灯の店にでも誘われそうです。
冗談はさておき、寒くなりましたね。風邪も流行っているようですので、
皆さん、体調には気をつけて、なるだけあたたかくしてお過ごしください。
さて、小川国夫の作品に関して、
「ガイド」が欲しい、とおっしゃる方へ、オススメの本を今日はご紹介しましょう。

2009年10月に静岡新聞社から出た、山本恵一郎『小川国夫を読む』(静新新書)。
山本恵一郎さんは、小川国夫本人からの依頼を受け、小川国夫自身はもちろん
周囲の人へのインタビューを長年に渡ってつづけてこられた、小川国夫の年譜制作者。
『東海のほとり』、『海の声』、『若き小川国夫』といった評伝本も書かれています。
この本では、小川国夫の初期~晩年の本をまんべんなく、順不同にとり上げて
解説していて、作家自身との交流、大阪の教室での様子を取材した記事や、追悼文なども収録。
「ガイド」なんて言い方をしましたが、小川文学を読み込んできた方にも
いろいろな発見があるかもしれません。
※12/5(日)ビジュアルアーツ専門学校大阪にて、
関西上映先行イベント“shellsong~耳よ、貝のように歌え”を開催します!
映画『デルタ 小川国夫原作オムニバス』上映はもちろん、
湯浅学さん(幻の名盤解放同盟) × 倉田めば(大阪ダルク)さんを
ゲストにお迎えしてトーク&朗読パフォーマンスを行います。
映画ファン、文学ファンの垣根を越えて、たくさんの方のご来場を
心からお待ち申し上げます。詳しくは、公式サイトをご覧ください!
下窪俊哉