12月21日(火)大阪シネ・ヌーヴォでの上映初日、『小川国夫生誕祭』の特別ゲスト司修さんの作品を少し紹介します。
本日紹介するのは、歴史学者網野善彦さんと司修さんとの共作『河原にできた中世の町』(岩波書店)という絵本です。なぜこの本を選んだのか、それには訳があります。それはこの絵本の舞台が<デルタ>だからなのです!
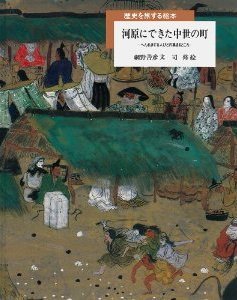
歴史学者網野善彦さんは、「日本=農耕民族社会」という概念にメスを入れ、それまで埋もれてきた海民や職人などが果たしてきた役割に着目し、日本社会の多様性を示してきました。その業績は、転換点にある現代においてさらに重要性を増していくでしょう。そんな網野善彦さんが、歴史学という領域から、絵本という全く異なる領域に挑戦したのが本書でした。『河原にできた中世の町』というタイトルになっていますが、河原を舞台とし、人類誕生前から現代までの壮大な時間の推移が絵巻物ふうに語られています。
網野さんのパートナーに選ばれたのが、司修さん。なぜ絵巻物を技法として習得した日本画の作家ではなく、幻想的な作風を得意とする司修さんが選ばれたのでしょうか。
その理由ではありませんが、この絵本をつくるための前提条件を網野善彦さんはこう語っておられます。
「司さんの目と私の目が重なって、同じ一つの目で対象が見えるようになるまでは決して作るまい」
司さんの耳を信じ、目にすべてを託せると網野さんが信じられたからこそ、このまったく類を見ない絵本が生みだされたのだと思うのです。
<平安時代末~鎌倉時代の中州と河原>の頁には、こんな文章が載っています。
中州や河原ではいろいろなことがおこります。そこはあの世に人を送り、あの世からの声を聞く場所でした。境で働く人びとがまずそこに住みつきます。

映画『デルタ』に関心を持って頂いた方には、是非手にしてもらいたい一冊、それが『河原にできた中世の町』です。
※『小川国夫生誕祭』は、メールでの予約も承っております。詳しくは下記を参照下さい!
http://www.cinenouveau.com/
井川 拓
司 修『風船乗りの夢』
12月21日(火)大阪シネ・ヌーヴォでの上映初日、『小川国夫生誕祭』の特別ゲスト司修さんの作品を少し紹介します。
本日紹介するのは、司修さんの画文集『風船乗りの夢』という本です。装幀家・画家としてだけでなく、文章という領域でも、司修さんの才覚が注目を集めた一冊といえるでしょう。

『風船乗りの夢』というタイトルは司さんと同郷の詩人萩原朔太郎の詩からとられています。メルヘンチックな響きの言葉ですが、ここに収められた絵、文章はある痛ましさを覚えずにはいられないものばかりです。そう、朔太郎の詩と同じように。
先日、司修さんのことを「旅人」と紹介しました。ひとはなぜ旅に出るのでしょうか。なぜ旅に病み、夢は枯野をかけぬけるのでしょうか。
その理由の一つは、「故郷を喪う」痛みに発するのかもしれません。

この本のあとがきには、小川国夫がこんな文章を寄せています。
「私は反射的に、彼の風景を思い浮かべる。青く果て知れない夢の地帯を思い浮かべる。私にはまだよく見極められないが、君は故郷へ立ち戻る人ではないようだ。行く手に故郷を見出し続ける人ではないのか。」
この文が書かれてから、三十年が経ちましたが、小川国夫の予測通り、司修さんの旅は果てしもなくまだ続いています。
小川国夫の誕生日に司 修さんがやってくるこの滅多にない機会をぜひお楽しみ下さい!
井川 拓
司 修『夢景色』
12月21日(火)は大阪シネ・ヌーヴォでの上映初日となりますが、この日は本映画原作者小川国夫の誕生日に当たります。そこで『小川国夫生誕祭』として、特別ゲストに作家・画家・装幀家の司修氏を迎え、映画上映後、対談を行います。
司修さんという名前は記憶しておらずとも、彼が装幀を手掛けた本を持っておられる方は多いと思います。小川国夫は勿論のもと、大江健三郎、安倍公房、中上健次といった文学者が司さんの絵に魅せられました。
司修さんは、映画の看板絵描きから、そのキャリアを始めました。独学で独自の技法を体得し、装幀だけに留まらない様々な分野で活躍されています。その旺盛で自由な活動ぶりから“風来坊”と称されることも多いようです。
司修さんのような方を、職業的な肩書で定義するってこと自体、間違っているかもしれません。まずなによりも旅人である、それが司修さんのより正確な肩書ではないかと思えるのです。
今日は、司修さんの旅行記『夢景色』(東京書籍)を紹介します。「幻想旅行記」とあるように、たんなる旅日記ではありません。実際に旅先で書き留めたスケッチと、司さん独特の幻想風景が入り混じった美しい書物です。

司さんの幻想は、どこかで少年時代の思い出と結びついています。いまと地続きにある過去を呼び覚ますという行為が幻想というかたちでなされていると言えるかもしれません。だからこそ時に暗く、ぞっとする筆致にもどこか懐かしさを感じたりもします。
司さんの少年時代と映画館は切っても切り離されない関係にあります。そんな司修さんが小川国夫について、映画『デルタ』についてどんな話をしてくれるのか、今から楽しみでなりません。

※本日紹介させてもらった『夢景色』はシネ・ヌーヴォでも閲覧して頂けます。
ぜひ手に取ってご覧ください。
※『小川国夫生誕祭』は、メールでの予約も承っております。詳しくは下記を参照下さい!
http://www.cinenouveau.com/
井川 拓
カウントダウン
大阪シネ・ヌーヴォでの公開が、いよいよ来週・火曜に迫ってきました!
(名古屋シネマテークでは、来週・金曜~土曜の上映です)
初日は19時~の上映で、上映後には司修さんをゲストにお迎えして
スペシャル・トークを開催予定!
(現在、シネ・ヌーヴォでは予約受付中です)
それから、上映期間中のロビーでは、映画『デルタ』や小川国夫にまつわる
小展示も行われます。(お時間ある方は早めにお越しいただいて、ご覧ください)

また、副読本『海のように、光のように満ち~小川国夫の《デルタ》をめぐって』や
小川国夫の著作の一部が販売にもなる予定。
『海のように、光のように満ち』は、私がたまたま映画『デルタ』上映委員会の皆さんと
出会い、ワイワイ喋りながら(?)つくった愛情たっぷりの一冊です。
私の文章だけでなく、映画『デルタ』のスナップなど写真も満載!
ぜひ劇場で、お手にとってご覧いただきたいと思います。
下窪俊哉
島尾敏雄と小川国夫
大阪、シネ・ヌーヴォでの公開が、迫ってきています。
その初回である12/21(火)19時~上映の後には、
画家・作家で、小川国夫の著作の装幀・装画をたくさん手がけた
司修さんをスペシャル・ゲストにお迎えして、
小川国夫や絵画、映画、文学に関するイロイロサマザマな話を
ご来場いただく皆さんと共有したいと思っています。
その司さんが装幀を担当した小川国夫の著作を、またひとつ。

1987年刊行の『回想の島尾敏雄』(小沢書店)。
多くの方がご紹介されているとおり、島尾敏雄さんは、
朝日新聞の「一冊の本」で私家版『アポロンの島』をとり上げて
小川国夫さんが世の中に知られるきっかけになった作家です。
その交遊は、無名時代の小川さん(静岡県藤枝市在住)を、
島尾さん(鹿児島県の奄美大島在住)が突然、訪問して以来、
1986年に島尾さんが亡くなるまでつづきました。
この本は、その島尾さんの死後に刊行された、追悼文を含む一冊。
司修さんによる装幀(箱)も、控えめではありますが、
どことなく“追悼”を意識したような渋いものになっています。
下窪俊哉
小川国夫と大阪芸術大学(続)
2日間に渡る大阪芸術大学での上映にご出席くださった
学生の皆さん、ありがとうございました!
どんな感想をお持ちになったでしょうか?
本ブログやtwitterなどを通して、ご意見・ご感想はどしどし
お待ちしておりますので、よろしくお願いします!
さて、その大阪芸術大学で、小川国夫さんの責任編集として
出していた雑誌には『河南文学』(創刊号~第12号)のほかに
2003年に2冊だけ刊行された『河南文藝 文学篇』があります。
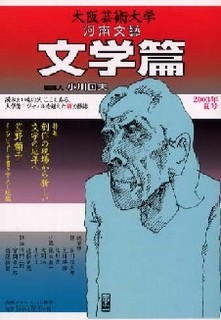
このように、小川国夫の肖像が表紙を飾った号もありました。
山藤章二さんのイラストです。
この号には小川国夫の大学での講義録が丸々一回分載っています。
「小説の方法」と題して、小川流の“ハウ・トゥー・ライト”を語ったものですが、
小説とは、「個人に深く関わること」だとしながら、
ホフマンスタールの言葉をひいて、自分の一生で耳に入ってくる“肉声”は
祖父祖母から孫の代、せいぜい曾孫の声までで、140年くらいか、と語っています。
まさに自分史です。ストレートな自分史ではないかもしれません。
もっと自由に拡大した自分史というものが、ぼくの小説です。
源氏物語は千年も昔の自分史ですよ。ぼくはその千年あとでも書くんです。
そう考えると、これは文学者のぼくの義務だ。紫式部がやったように
ぼくはぼくのフィールドでそれをやるんだという考え方が自然と出てくると
思うわけです。それが我々が文学をやる上の、
一つの基本に据えるべき考え方だと思います。
こういった話を重ねるなかで、生前最後の随筆集となった
『夕波帖』収録の「耳を澄ます」などの考え方が生まれたのだと感じます。
その話は、また。
※12/21(火)シネヌーヴォ初日上映&トークショーの予約の受付を
行っています。詳しくは、コチラをご覧ください。
下窪俊哉
小川国夫と大阪芸術大学
本日(12/13)から明日にかけて、大阪芸術大学の映画館にて
映画『デルタ 小川国夫原作オムニバス』の上映をさせていただいております。
映像学科の学科長で映画監督の大森一樹さんはじめ、
大阪芸術大学の関係者各位へは、心からお礼を申し上げます。
大阪芸術大学は、本映画の原作者・小川国夫さんが晩年の約16年、
文芸学科教授として深く関わった場所です。
学生の皆さんに、本映画がどのように届くのか、楽しみです。

その大阪芸術大学で、小川国夫さんを編集人として出していた雑誌があります。
『河南文学(かなんぶんがく)』という雑誌です。毎号の巻末には、
「編集後記に代えて」として、小川国夫さんの文章が掲載されていました。
創刊号の編集後記(に代えて)は、「文学的青春」というタイトルで、
後に『昼行燈ノート』(文藝春秋)に掲載されたものですが、単行本に掲載されている
文章とは、少しだけ雰囲気が違います。
ここで小川さんは、自分たち仲間で創刊した同人雑誌『青銅時代』の思い出について
書いています。私は大阪で小川さんと出会ったひとりなのですが、
この文章は、おそらく一生忘れないでしょう。
不幸から脱すること、癒えることを理想とした文学者は、自分に固有なこの軌道にひっそりと乗っている(あるいは乗ろうとしている)星のようなものだ。しかしこの星のかたわらには、軌道に乗ることをうけがわず、破滅を急ぐ星もある。その時その星は一きわ光を益すので、私は逃げて行く蛍を掌に収めようとするかのように、空しく手を伸ばしたものだ。そして闇を掴んで悲観にくれた悪夢に似た思い出は、もう二十二年も前のことなのに、まだ身近にある。
ここで「二十二年前」と書いてあることは、1991年の時点ですから、
いま、この時点で、約41年前の話です。
小川国夫さんの「文学的青春」は、大丈夫、まだ受け継がれているよ、
と呼びかけたい気がしています。
下窪俊哉
恋愛小説
小川国夫の小説には、若い男女の交わりを、すごく感覚的に
スケッチふうに書いた小品が幾つもあり、印象に残っています。
映画「誘惑として、」に登場する男女のエピソード
(短篇「駅の明り」を原作とする部分ですね)も、
そのエッセンスを伝えていると感じます。

短篇集『流域』のトップに収録されている「心臓」も、そういった作品のひとつ。
(画像は、集英社文庫版)
小川国夫のこの手の小説を、説明することは、どうしても難しくて、
良さを感じていただけるとしたら、本文をご紹介するのが一番良いのではないか、
と感じてひいてみます。
体についた綾子のにおいがした。蝉の声が夜気を引っ掻いた。一面の虫の声の底を、川が流れていた。彼は自分の動悸を聞きながら、この音だけが自分なのか……、と思った。騒ぐ血を肉の容器が柔らかく受け止め、ゴクンゴクンと波動を胸壁にぶつけていた。それも動物の感触だったが、一糸乱れないのが彼には不思議だった。どんな動物も体に心臓を持ち、混乱する意志と行為をよそに、揃って整然とこの音をさせている。そう感じながら、彼は長い間耳を澄ましていた。
とっても内省的な世界ながら、人間の「内面」に向かうというよりも、
音や、自然や、肉体といったモノに向かっているのが印象的です。
この本も久しく手に入らない状態がつづいています。
が、このアンソロジーは現行商品で入手可能でしょうか?
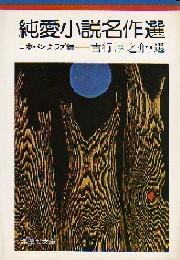
吉行淳之介選の『純愛小説名作選』(集英社文庫)。この本を開くと
島尾敏雄さんの「ロング・ロング・アゴウ」などと共に「心臓」も収録されています。
※12/21(火)映画『デルタ』シネヌーヴォ公開初日、19時~上映後に
小川国夫さんとも親交の深かった画家・作家の司修さんをゲストに、
本映画のプロデューサー仲田恭子とのトークショーを開催します!
シネヌーヴォでは予約受付を開始しています。お見逃しなく!
http://www.cinenouveau.com/news/news.html
下窪俊哉
遊子随想~旅の本
12/21のスペシャルゲスト・司修さんにちなんで、
司さんと小川国夫さんの“共演”作を今日も一冊。

1989年6月発行の『遊子随想』(岩波書店)は、
装幀だけでなく、本文中に置かれている絵も司修さんによるもの。

この本が刊行された当時、司さんの個展“遊子随想展”も開催されたとか。
司修『影について』(講談社文芸文庫)の巻末に置かれた
著者自身による“年譜”ではこの個展に触れて、
打ち上げで小川国夫さんと酒を「飲みすぎ」た出来事が
ユーモアたっぷりに書かれています。
『遊子随想』は、著者自身の、若き日のヨーロッパ放浪の旅を中心に
書かれた《旅》のエッセイ。傑作です。が、残念ながら現在は絶版。
ご興味もたれた方は、図書館か古本屋で探してみてください。
下窪俊哉
shellsong 報告その1「キリガミロイ」
12月5日(日)ビジュアル・アーツ専門学校大阪で行われたイベント“shellsong 耳よ、貝のように歌え”に、多くの方にお集まりいただき、誠にありがとうございました。
映画の上映・朗読パフォーマンス・対談という三本立てで行いましたが、今日は、朗読パフォーマンスについて紹介します。
朗読で扱ったテキストは、小川国夫原作の「キリガミロイ」という作品です。(『血と幻』収録)
「神」、「汚鬼」、「荒野(あらの)」、「ゲヘナ(地獄)」という言葉は僕たちが生きる日常のなかでは耳慣れないものですし、遠い世界の出来事のように思われたかもしれません。
それでも敢えてこの作品を選んだのは、遠い世界の出来事のようでいながら、僕たちが抱えた大きな問題と通底するものがあると感じたからです。
朗読は、音楽著述家であり、フォーク・ロック・バンド「湯浅湾」のリーダーである湯浅学さんと、「大阪ダルク」代表として薬物依存者のピアサポートを行う倉田めばさんに行って頂きました。
所謂「朗読」に親しんだ方にとっては、少し違和感を持たれたかもしれません。
喉の手術を行い、自らの声のキーがどこにあるか分からない倉田めばさんの声は、時に鎖を引き摺るように地を震わせ、時に蜻蛉のように宙に消え入りそうでした。
「汚鬼」、そしてその対照となる人物になり変わった湯浅学さんは、朗読の途中に挟み込まれたギターの即興演奏で、朗読という一方向に過ぎてゆく時間のなかに、時に堰となり、時に逆流するもうひとつの時間を紡いでいました。
会場には一種異様な緊張感が漂っていました。
ふたりの声とギターを通して、小川国夫が残した言葉はもういちど音に還り、物語は誰のものでもなく、語り手と聞き手のあいまを漂うことができたのかもしれません。それはひょっとしたら、僕たちが最初に聴いた音楽にちかいかもしれません。きっとそれは闇のなかから聴こえてきて、僕たちをここへ導いてくれたのだと思います。
そんなふうに感じられたのも、二人の朗読者の声に耳を預けてくれた方がいらっしゃたからこそだと思います。会場の一番後ろから見ていて、朗読者の声、ギター、とともにみなさんのふたつの耳も“楽器”のように映りました。どんな音が鳴っているのかそれは聴こえませんでしたが、なんてチャーミングな楽器なんだろうと胸高まった瞬間があったのも事実です。
このような素晴らしい場を創って頂いたみなさまに心より感謝いたします。
ありがとうございました。
井川 拓